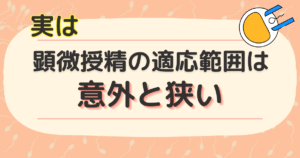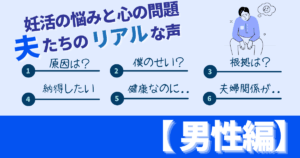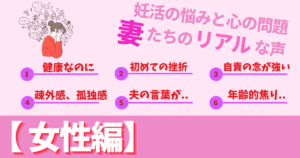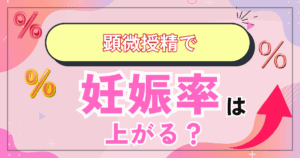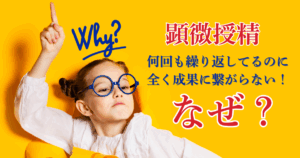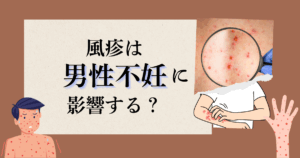だけ で「人工的に授精」させられる という利便性があるため、その適応範囲が広がり、生殖補助医療の主流になっています。治療現場で「精子の数が少ない!」「精子の動きが悪い!」となり、一般精液検査で世界保健機構WHOの診断基準を満たしていなければ、即 男性不妊と診断され、顕微授精に展開されます。しかし実は、悪い状態の精子を 顕微授精に用いた場合、生まれてくる子どもに悪影響を及ぼさない! という、 出生児への安全性に関しては未だ不明な点が多い のも事実です。 陰に存在する「リスク」を正しく理解 し、それぞれのご夫婦にとって「適切で安全な」不妊治療を選択 されること を切望します。すでに不妊治療中のご夫婦はもちろん、これから不妊治療をしようと考えているご夫婦が、正しい 生殖補助医療の知識 を身に付けて「効率的な」 不妊治療をしてください。
目次
DNA損傷精子が顕微授精の対象となってしまう確率が高い理由は?
DNA損傷精子が顕微授精に用いられる確率が高くなる理由について解説する前に、 体を作っている細胞(体細胞)のDNA修復機構についてお話します。
一般的な皮膚や肝臓などの体細胞には、DNA修復機構 という、遺伝情報DNAの傷を修復する機能が備えられています。そのため、多少ならば傷ついたDNAは修復されますので、問題がない わけです。ヒトの卵子は、体細胞と同じようにDNA修復機構を備えていますので、卵子DNA損傷はDNA修復酵素によって回復する ことが可能です。
しかし、ヒトの精子は卵子と違って特殊な細胞ですので、精子形成過程でDNA修復能力を失います。 その結果として、解りやすく言えば、妊孕性が認められた健康な精子を造ることができる男性においても、 一部は損傷したDNAが修復されないままDNA損傷精子として残存し、運動精子の中に混在 正常に精子を造る機能を有する男性の精子も完璧ではない! ということです。不妊男性 の精子においては、「精子数の減少」 や「運動率の低下」 が指摘されますが、 実は DNA損傷をはじめとする機能異常精子の比率が高くなる 傾向があります。この 点に着目し、慎重な対応が必要になりますが、卵子に注入する精子にDNA損傷がない!という科学的な根拠がないままに 、顕微授精に展開されています。結果として「DNAが損傷された運動精子」が顕微授精に用いられる 確率が高く なるということです。 ここに 『顕微授精のリスク があります(詳細は後述) 。
見かけだけでは精子機能の異常を見極ることはできない!
治療現場では、精子の運動性に着目し、「運動精子=良好精子」という性善説に基づいた指標で精子を選んでいます。確かに精子の運動性は必要条件ですが、必ずしも十分条件ではありません。見栄えの良い元気そうな「運動精子」であっても、DNAが損傷されている精子である可能性 があります。 つまり、ヒト精子においては性善説は成り立っておらず、見た目だけではDNA損傷をはじめとした精子機能異常を見極めることはできません。
前述していますが、治療対象になる男性不妊の方においては、精子DNA損傷率が高い 傾向を認めます ので、安全性の高い顕微授精を実施するには「正常に見える運動精子」の中から「DNA損傷精子」を事前に排除 して、 言い換えれば 「DNA損傷のない精子」 して、 安全な精子を穿刺注入 できるか否か?を正確に判定できることが極めて重要
顕微授精児と発達障害の関係に関する研究
ここまで顕微授精にDNA損傷精子が用いられることへの懸念についてご説明してきましたが、欧米では「自然妊娠によって生まれた子どもより、顕微授精によって生まれた子は先天異常発症率が比較的高い」 という報告が多数あります (※1)。
例えば 2015年には、コロンビア大学教授 ピーター・ベアマン氏らが長期にわたる大規模疫学調査の結果を『American Journal of Public Health』という雑誌に報告しています。その内容は「顕微授精に代表される生殖補助医療で生まれた子どもは、自然に妊娠して誕生した子どもに比べ、自閉症スペクトラム障害(社会性、コミュニケーション、行動面の困難を伴う発達障害の総称)であるリスクが2倍 である」 というものです。このデータはアメリカ疾病対策予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)が所管し、CDCは「顕微授精にはリスクがある」という見解を出しています。
また国内でも 2011年には、厚生労働省科学研究班の生殖補助医療出生児に関する調査において「顕微授精・胚盤胞培養・胚盤胞凍結保存の人工的な操作を加えるほど、出生児の体重が増加する」 ことが報告されました。この現象は、ゲノムインプリンティング異常(遺伝子の働きを調整する仕組みに異常が出る病態) による、胎児過剰発育である可能性が高いと指摘されています。先天異常を専門とする医師らも『顕微授精や胚盤胞培養のリスク』を危惧する研究成果
※1 MJ. Davies, VM. Moore, KJ. Willson, et.al. (2012) Reproductive Technologies and the Risk of Birth Defects, The New England Journal of Medicine, 366: 1803-1813.
※2 有馬隆博, 岡江寛明, 樋浦仁(2012)
国内では、発達障害との関連性を含む「顕微授精のリスク」が軽視されている
上述していますように、アメリカCDCは 「顕微授精と自閉症スペクトラム障害の関係の間に因果関係がないとは言い切れない」 という見解 を出しており、 また日本でも「ゲノムインプリンティング異常」 を指摘していますが、日本における顕微授精への危機管理意識は総じて低い現状にあります。海外に比べて先天異常に対して目が向けられることが少なく、未だに「顕微授精は安全で、自然妊娠と同程度のリスクです」と説明される傾向にあります。
正直なところ、精子異常と顕微授精と発達障害の間に因果関係がないことを科学的に証明することは、極めて困難 黒田IMR 院長の私は、命を造り出す生殖補助医療に携わる者として、顕微授精の安全性が保証されていない現況だからこそ、また「顕微授精にはリスクがある」というCDCの見解だからこそ「因果関係はある」という前提で危機管理を徹底する必要がある と考え、安全戦略に努めています。
安全な顕微授精の実施には「精子の品質管理」が必須!
顕微授精では、精子の量的(精子数)不足こそ補うことができますが、DNA損傷をはじめとする精子の質的(精子機能)異常をカバーすることはできません。顕微授精を実施する際は、大前提として、まず精子機能の精密検査を行い、穿刺注入する精子の質が良いこと(DNA損傷をはじめとする機能異常のない精子であること)を確認しておく必要
しかし繰り返しになりますが、治療現場では、これらの前提が広く普及していない状況にありますので、「精子の状態が悪くても、1匹でも精子がいれば顕微授精で妊娠可能です。顕微授精は安全です」と語られ続けています。その結果が、顕微授精による出生児へのリスクにつながっている可能性は否定できません。
黒田IMRでは、院長を含む精子研究チーム(詳細は、黒田IMRホームページを参照ください)が開発した、DNA損傷をはじめとする機能異常精子を事前に排除する技術、 ならびに、 精子機能を正確に調べることができる分子生物学的な検査手法 を用いて、治療に用いる精子の品質管理を徹底 事前に 精子機能を高精度に検査して、科学的根拠に基づいた詳細情報を得ることにより、精子機能が正常で、安心して卵子に注入できる安全な精子か否かを判断 しています。結果として、 安全性の高い顕微授精を実施する
まとめ
命を作り出す不妊治療において、安全が何よりも優先されなくてはなりません。危険な精子を選んでしまう可能性を下げるためには、事前の精密検査にて精子の状態を正確に確認した上で、高度な技術によって安全性の高い精子を選別する必要があります。
不妊治療のゴールは妊娠ではありません。顕微授精をはじめとした生殖補助医療によって誕生した子ども達が、心身共に健康に成長し、平均寿命まで元気に過ごせること です 。
妊娠を望むご夫婦には、改めて正確な知識を身に付けていただく ことを願います。ご夫婦それぞれの不妊原因を正確に解析 した上で、お二人にとって適切で安全な治療方法を選択 してください。
DNA損傷精子と発達障害に関するよくある質問
精子のDNA損傷は、子どもが障害を持って生まれる原因となりうるのでしょうか?
ヒト精子は粗雑に量産されますが、その過程に沢山の遺伝子が複雑に関わります。この「粗製乱造」の精子形成メカニズムが「造精エラー率」を上げ、「DNAのコピーミス」を起こします。 また「DNA修復機構を持たない」 という精子の特性もあり、傷ついたDNAが修復されないまま損傷精子として残存します。
結論から言えば、このDNA損傷精子(DNA断片化陽性精子)が妊孕性を下げて「不妊」の原因になったり、また卵子と受精した場合には「流産」の原因になったりしますが、最も怖い点は「出生児の健康に悪影響を及ぼし、子どもの障害につながるリスク」があることです。
もう少し詳しく説明しますと、精子DNA損傷の程度が重度な場合は、卵子と受精して胚の発生が進んだとしても、大半は自然に淘汰されて流産しますので、生命の誕生に至りません。一方で、損傷の程度が軽度なDNAの僅かな傷を持つ精子は、流産を免れて出産に至ります。 その際に、精子の軽度なDNA損傷が、卵子が備えるDNA修復機構によって完全に修復されれば、生まれてくる子どもに悪影響を及ぼすことはありませんが、不完全に修復された場合は、出生児に何らかの異常を発症させるリスクにつながります 。つまり、精子の軽度なDNA損傷こそが出生児へのハイリスクになります 。
そのため不妊治療においては、事前に精子DNAの傷の状態を正確に検査できること、同時に、精子の高度な選別技術によりDNA損傷精子を排除できることが必須になります。
父親の精子の状態は、子どもの発達障害のリスクに関連しているのでしょうか?
精祖細胞から その都度 造り出されているヒト精子の形成には、およそ74日かかりますが、その間に沢山の遺伝子が複雑に関わり、凄い数の精子を造り出します。この「粗製乱造」のメカニズムが「造精エラー率」を上げ、「DNAのコピーミス」を起こします。 解りやすく言えば、どうしても「質より量」になり、結果として精子の「質的バラツキ」を生み出します。さらに「DNA修復機構を持たない」 という精子の特性も手伝い、傷ついたDNAが修復されないまま「DNA損傷精子」として残存します。
つまり、造精機能が正常な男性の精子が全て完璧というわけにはならず、どうしても健康な精子の中に異常な精子が混在してきます。 この異常精子の比率が高くなり、男性不妊の原因になる場合は、造精過程に関わるDNAのコピ-ミスが起きている割合が高いケースで す。この頻度と程度にもよりますが、DNAコピ-ミスがある異常精子が受精に関わり、命の誕生に繋がった際には、出生児の神経発達障害発症率が上がる傾向がある
そのため不妊治療においては、事前に精子DNAの傷の状態を正確に検査できること、同時に、精子の高度な選別技術によりDNA損傷精子を排除できることが必須になります。
一般的な精液検査で、将来の子どもの発達障害のリスクを予測することはできますか?
現在、一般的に行われる精液検査(精子の数、運動率、形態など)で、将来の子どもの発達障害のリスクを予測することは困難です。
一方で、黒田IMRで実施してる分子生物学的な手法を用いた精度の高い精子検査 では、一般精液検査では検知できない「精子の中に隠れ潜んでいる異常」を解析 できます正確な精子妊孕性に関する詳細情報を取得 できますので、精子が及ぼす「次世代の疾患リスク」を ある程度 予測する

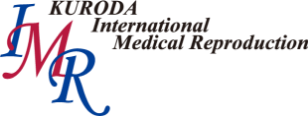

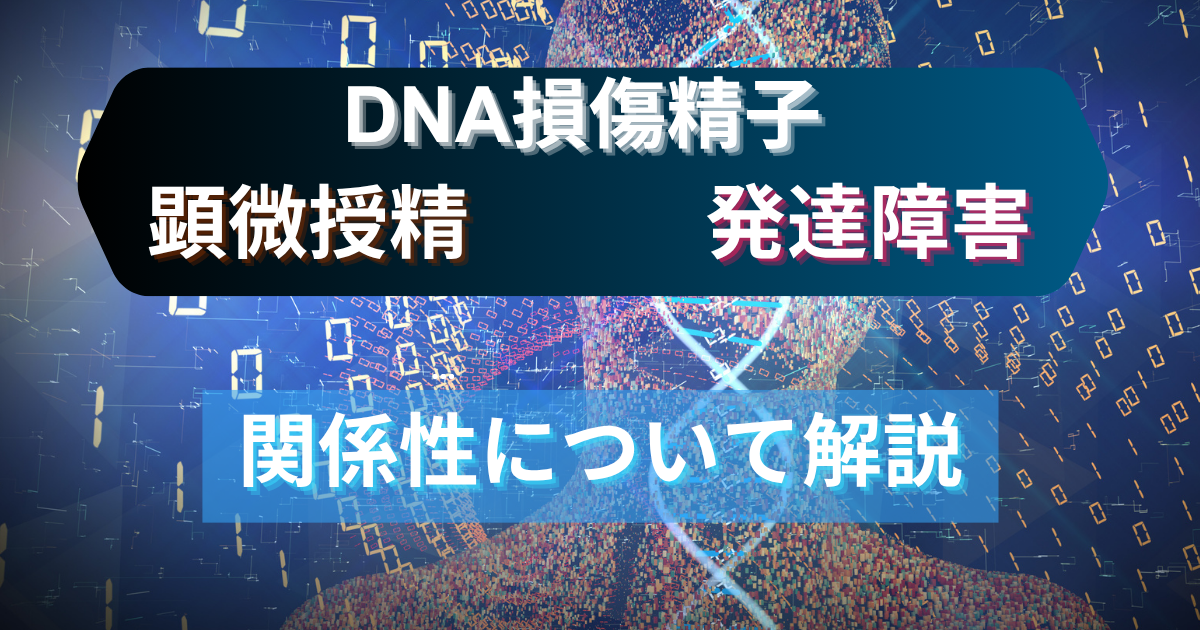
-3-3.png)
-3.png)