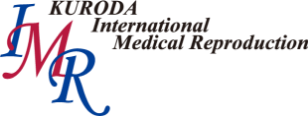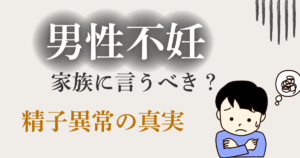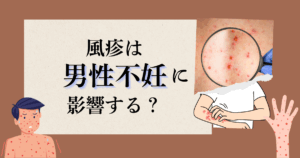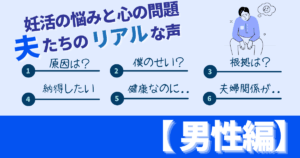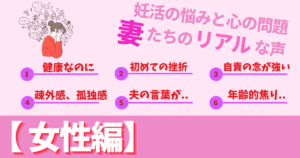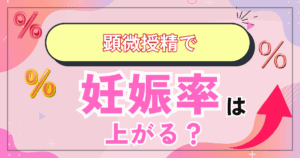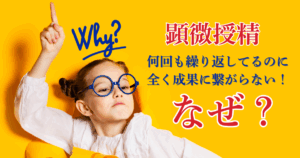私たち昭和30年代生まれの女性には、適齢期になったら結婚をして、なるべく早く子どもを産むことが望まれていたような風潮でしたが、そこから半世紀以上の時が流れ、今では多くの女性が社会進出して仕事を持つ時代になりました。そのような社会的な背景の中で「いつかは子どもが欲しいな?」「いつかはお母さんになりたいな?」という思いを持ちながら「今は未だ・・・」という気持ちの女性も少なくないのではないでしょうか?
目次
現代女性が抱える妊活の悩み

- キャリアーアップを目指して頑張る日々も充実しているし、今まで頑張ってきたし・・・
- その一方で、彼との子供も欲しいし・・・
- 周囲で出産する友達も増えていく中、歳は重ねて卵子はどんどん老化していくし・・・
- どこかで置いてきぼりにされている?感じで、孤立感があるし・・・
仕事を持つ女性の悩みは沢山あることでしょう。
そのよう悩み多き女性にとって「卵子凍結という選択は、夢のような技術が登場した!」と思われることでしょう。現実問題として「いざ、妊活!」となりますと、「卵子凍結」を選択する女性と「不妊治療」を選択する女性と二極化しています。
卵子凍結に関してはメリットとデメリットがありますが、詳細は黒田IMRのコラム『卵子凍結保存の課題【専門医】が詳しく解説』をご参照ください。
この記事では「いざ!妊活」となって不妊治療を選択するご夫婦の「いつまで頑張ればいいの?」「不妊治療の止め時は?」「妊活の期間」についてお話します。
妊活を始める前に知っておくべきこと
まず!この記事を読んでくださっている方が、少しでも『上手な妊活』が出来ますように!と願いつつ、冒頭で衝撃的な結論からお話したいと思います。
私のもとには毎日、長い不妊治療のあるご夫婦が相談に見えます。その大半が「顕微授精を何回も繰り返しても全く成果に繋がらず、結果として奥様の年齢が高齢化してしまった」という二重苦に陥った顕微授精反復不成功のご夫婦です。
正直なところ、顕微授精反復不成功のご夫婦を対象に、私たち精子研究チーム(詳細は、黒田IMRのホームページを参照ください)が開発した、精子の質(精子機能)を正確に調べられる精密検査をしてみますと、その約8割に夫側の精子の問題が発覚します。皆さんは、どういうことか?と思われることでしょう。その回答を解りやすく解説しますので、最後までお読み下さい。
不妊の原因は男性側にも半分ある
世間一般では、まだまだ「赤ちゃんができない!」となりますと女性側の問題と捉えられる傾向にあり、実際に不妊治療が開始されますと、最初に女性側に多くの不妊検査が行われるという流れが一般的です。しかし実は、不妊になる原因の約半数は男性側の精子の問題(精子異常)なのです。また男性側の不妊検査は主に「精液検査」になります。言い換えれば、精液検査だけ(とは言えませんが)になります。
女性の年齢と妊娠率の関係性
女性が妊娠・出産を目指すにあたり知っておきたいポイントは、卵巣や子宮に問題が認められないのならば、年齢が若ければ若いほど妊娠率は高いということ、逆に流産率は低いということ、結果として出産率が上がるということです。要するに、女性の年齢が若ければ若いほど子どもを産める可能性、母になれる可能性が高くなるということです。
男性の妊孕性と年齢の関係は複雑
一方で、男性が女性を妊娠させられる精子力(精子妊孕性)は、年齢に直結しませんので厄介です。解りやすく言えば、精子妊孕性の良し悪しには、先天性(生まれつき)の遺伝子の問題が関与していますので、年齢が若くても精子妊孕性が低い方がいらっしゃる一方で、高齢な男性の精子でも高い妊孕性を保持できている場合もあるということです。男性側の精子妊孕性は、女性のように年齢に直結するという単純な話ではない!ということです。
効率的な妊活の第一歩とは?
そこでお伝えしたい重要ポイントですが、「いざ!妊活」となりましたら、最初に男性側の精子の精密検査を受けて下さい。最も効率的な上手な妊活法になります。
精密検査で先天性の精子異常が認められ、精子妊孕性が低いと診断された場合には、どんなに女性側の治療が上手くいっても(女性側の妊孕性が高くても)、治療は難航する傾向にあります。このような場合には、医療機関における治療技術の精度にも左右されますが、生殖補助医療による不妊治療を3回(多くても5回程度)実施しても成果に繋がらなければ一度治療の停止、中断をして、その後の治療断念を視野に入れてご夫婦でよくお話し合いをされることをお勧めします。
一方で、精密検査の結果、先天性の精子異常が否定された場合には、医療機関の技術精度にもよりますが、生殖補助医療による不妊治療を3回実施したら成果に繋がる可能性が高いと思います。
どちらのケースにしても、治療期間(年月)については1年間に集中して複数回の治療をされるご夫婦もいらっしゃる一方で、1年に1~2回のペースで治療を試みるご夫婦もおられ、夫婦毎にかなり差がありますので、一概に妊活期間は何年がお勧めです!とは言えません。しかし治療回数として考えた場合、3~5回程度実施された結果を踏まえて「治療の止め時」をご夫婦で検討されたら よろしいのではないでしょうか。また女性の年齢が高い場合には、なるべく時間的な効率化を図って治療に臨まれることをお勧めします。
女性が感じる限界と男性不妊の葛藤
女性の場合は、高齢化に伴って生理周期や基礎体温の乱れ、生理周期に伴う自覚症状の消失感、体の衰え等々、いろいろな点で「そろそろ難しいな?」という自覚に至ることも少なくありません。
しかし男性の場合は、前述していますように、年齢に伴う自身の衰えとは別の問題、生まれつきの問題(遺伝子の問題)で精子妊孕性の限界を受け入れなくてはなりません。ここに心の葛藤が生じます。またパートナーとの関係性にもお互いの心の譲歩が必要になります。まさに男性不妊治療は深刻です。
精子異常が見逃されることで起こること
冒頭で申し上げました、私のもとにご相談に見える「顕微授精反復不成功」のご夫婦を対象に、黒田IMRの精子の質(精子機能)を正確に調べられる精密検査をしてみますと、その約8割に夫側の精子の問題が発覚した原因は、先天性の精子異常が見逃されたまま(一般精液検査では検知できませんので)顕微授精が繰り返されてしまい、結果として成果に繋がらない治療が継続されてしまったということです。
このような非効率的な不妊治療に陥らないためにも「いざ、妊活!」となりましたら「最初に精子精密検査!」という認識で進めていただけましたら、効率的な上手な妊活になります。
治療に向き合う上で夫婦の協力が不可欠
実際に不妊治療を開始しますと、仕事をもつ女性は受診日数も多くなりますので、スケジュールの調整に苦労される方も多いことでしょう。また痛みを伴う検査や治療もありますので、正直なところ、男性側より色々な負担がかかります。とくに女性側の精神的なストレスが大きくなりますので、そのメンタルケアを男性側に心得ていただくためにも、事前にご夫婦でよく話し合って、「妊活=不妊治療」における覚悟を共有して協力し合える関係性を構築しておくことが必要です。
命の尊さと感謝を知ること
とかく不妊治療は「不」が付くこともあり、「ネガティブ」な面ばかりが強調されますが、治療を通して、気づかなかったことに気づいたり、見えなかったことが見えてきたり、人間としての視野が広がることにも繋がりますので、悪いことばかりではありません。
私たち人間は「精子と卵子の奇跡的な出会い」によって誕生できた「尊い命」だということに気づくでしょう。そして その「命を大切」にしていかなくてならない気持ちになることでしょう。また生んでくれた「両親への感謝」の気持ちも深くなることでしょう。
さらに不妊治療を「している方」「してきた方」「しようと思っておられる方」、それぞれの気持ちに心から寄り添えることでしょう。それは、心豊かな素敵な人間性に繋がります。
「産んでも、産まなくても」「子どもがいても、いなくても」充実した人生を送れることが幸せなこと!と思えるように願って記事を終えます。
まとめ:まずは精子異常を正確に把握することから
男性不妊、とくに「精子異常」は深刻な問題です。だからこそ、精子の問題をなるべく早い時点で正確に把握して、その方の「精子異常のタイプに合った、安全で適正な治療法を選択できるか否か」を見極めることが大切です。
黒田IMRは、精子側の関連技術に特化しています。その背景には、院長が現在に至るまでの約40年、ヒト精子の研究を専攻し、研究チームと共に、安全かつ有効な精子側の関連技術を開発してきたという裏付けがあります。とくに男性不妊の検査と治療に力を注いでいますので、ご心配な方は一度ご相談にいらしてください。