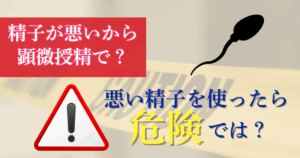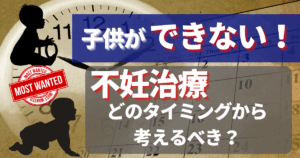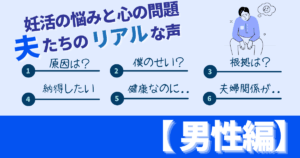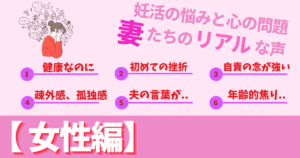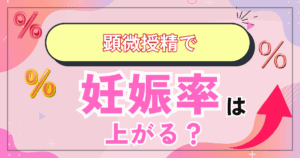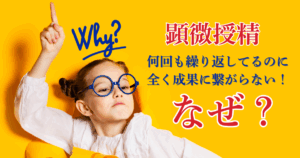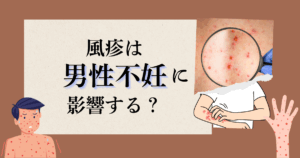2020年以降、私のもとには「顕微授精で生まれてくる子どもの健康状態」 に不安をもつ多くのご夫婦が相談にみえます。とくに「顕微授精と発達障害との因果関係を知りたい」 ので「精子の状態を詳しく検査してください」 という趣旨で受診されるご夫婦が増えました。ご相談いただいた内容を少し紹介します。
目次
顕微授精で発達障害の子どもをもった親たちの声・・・
○ 顕微授精で直ぐに授かりました。元気に生まれて5年。その一人目の子どもが「発達障害」の診断を受けました。二人目を悩みます。
○ 妻の年齢が若い(20代後半)のに、「精子の状態が悪い」ということで顕微授精を勧められ、何回も繰り返しました。受精率が悪く、胚移植になっても着床しないので、諦めようかと考えていた時、顕微授精6回目で奇跡的に着床、妊娠、出産となりました。その子が「自閉症スペクトラム障害」の診断を受けました。たまたまかもしれませんが、妻が若いだけに、これからの妊娠が不安です。
○ 「精子の状態が悪いので顕微授精をしましょう」と言われました。最近「顕微授精で自閉症が生まれる確率が高い」と色々なところで目にします。海外の論文も読みました。顕微授精しても大丈夫ですか?心配です。
日本では、 学会に登録をしている限定した医療機関だけが、年間に実施された生殖補助医療(体外受精や顕微授精など)の臨床 つまり、生殖補助医療で生まれた全ての子どもを対象にしているわけではありません ので、 『先天異常児の発症率に関する調査』も その限られた施設内における実施に留まっています。子どもが成長している過程で診断が可能になる 「自閉症スペクトラム障害」「注意欠陥多動性症候群」「精神発達遅滞」などの神経発達障害は含まれていません 海外では、すでに『長期に及ぶ大規模な疫学調査』 が実施 されており、顕微授精で生まれた子どものその後に関する傾向を打ち出しています 今後は日本にいても、疫学調査の結果を正確に数値化するために、限定した施設のみならず、生殖補助医療で出生した全ての子どもが少なくとも成人するまで追跡し得た『長期大規模疫学調査』 が実施されることが急務 です。
海外の長期大規模疫学調査の結果と見解
海外では 、2015年 コロンビア大学教授のピーター・ベアマン氏らの長期大規模疫学調査 の結果が『American Journal of Public Health』という雑誌に掲載されました。その内容は、カリフォルニア州で 1997〜2007年 に出生した 590万例 の小児に関するデータを元に分析 されたのもので、「顕微授精に代表される生殖補助医療で生まれた子どもは、自然に妊娠して誕生した子どもに比べ、自閉症スペクトラム障害 であるリスクが2倍 である」 という調査結果の報告でした。アメリカ政府のアメリカ疾病対策予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC) 「従来の体外受精と比較して、顕微授精が用いられた場合、生まれた子どもには自閉症スペクトラム障害と診断される傾向が高かった」 として発表し、主要な調査結果として所管しています。「顕微授精に代表される生殖補助医療技術が自閉症スペクトラム障害のリスクに有意な影響を及ぼす可能性がある」 と述べています。
海外では、自閉症スペクトラム障害の急激な増加と生殖補助医療の普及との関連性を指摘 する報告は多数あり、「顕微授精と自閉症スペクトラム障害の関係の間に因果関係がないとは言い切れない」という見解 を出して います。
命を造り出す生殖補助医療において「疑わしきは避けるべき」
冒頭でも申し上げていますが、顕微授精に代表される生殖補助医療で生まれた子どもと「発達障害」との因果関係に関する明確な結論を得るためには、基礎研究と共に多数の臨床症例を解析した長期大規模疫学調査が必要であり、そこには50年、80年いやそれ以上の相当の時間を要します。両者の間に因果関係があるという前提で「疑わしきは避けるべき」 という考え方を優先すべき 顕微授精と自閉症スペクトラム障害を含む神経発達障害との間に「因果関係がない」ということを科学的に証明することはできません。 黒田IMRのホームページを参照ください )が Post-ICSI として開発した 高効率媒精・卵管型微小環境体外受精法『人工卵管法』 により、顕微授精を回避できる 『顕微授精のリスク』 をご心配されているご夫婦は、一度ご相談にいらしてください。
顕微授精と発達障害リスクに関するFAQ
顕微授精で発達障害のリスクがあると言われる本当の理由は何ですか?
発達障害の発症には複数の要因が複雑に絡み合っていますので、原因を一つに特定することはできません。しかし顕微授精で生まれた子どもに発達障害の発症率が高いという報告は多数あり、その背景に、新生突然変異(遺伝子異常)に起因する異常精子が受精に関与したことが影響している可能性 を否定できません。「怖さ」 があります。異常精子が顕微授精に用いられた場合、出生児の発達や健康に悪影響を与えるリスク要因 になります。
一般的な不妊治療クリニックでは、リスクのある精子を見分けられないのですか?
良好精子に見える元気に泳いでいる精子(運動精子)の中には、出生児にハイリスクになるDNAが損傷した異常精子 が混在していますが、一般精液検査(普通の顕微鏡)では見えません 。この精子DNA損傷を正確に見抜くためには、特殊な分子生物学的な検査法が必要です。しかし残念ながら、異常精子を見分けることができる「高精度な精子評価法」や、それらの異常を持った精子を排除できる「高度な精子選別技術」を持っている専門施設は極めて少ないのが実情です。
黒田IMRの生殖医療は、なぜ出生児の発達障害のリスクを抑えられるのですか?
黒田IMRの生殖医療が出生児の発達障害のリスクを抑えられる理由は、事前に分子生物学的な手法で「高精度に精子の異常を調べる」 ことができ、また高度な精子選別技術により「DNA損傷精子を始めとする異常精子を排除する」 ことができる『特殊技術』を持っているからです。安全性の高い精子を選別回収した上で、安全な受精環境に展開すべく技術努力をしています ので、リスクを限りなく低減化できます。
黒田IMRの高度な精子選別技術についてはこちら

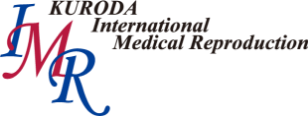

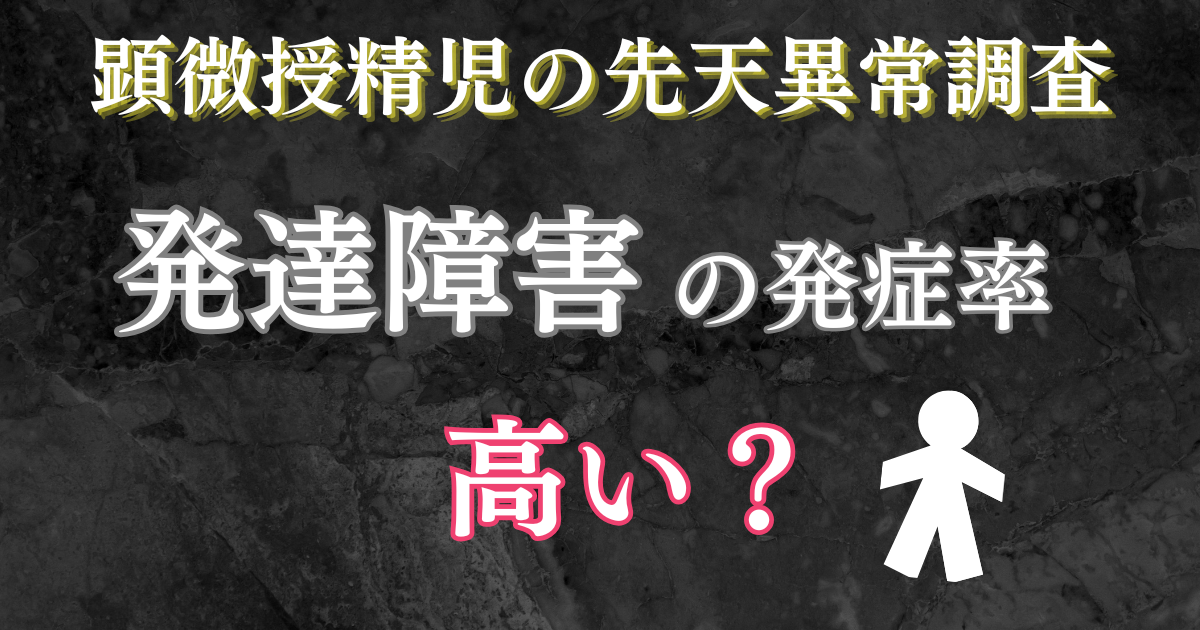
-1-2.png)