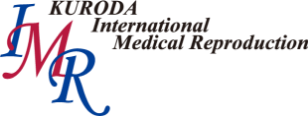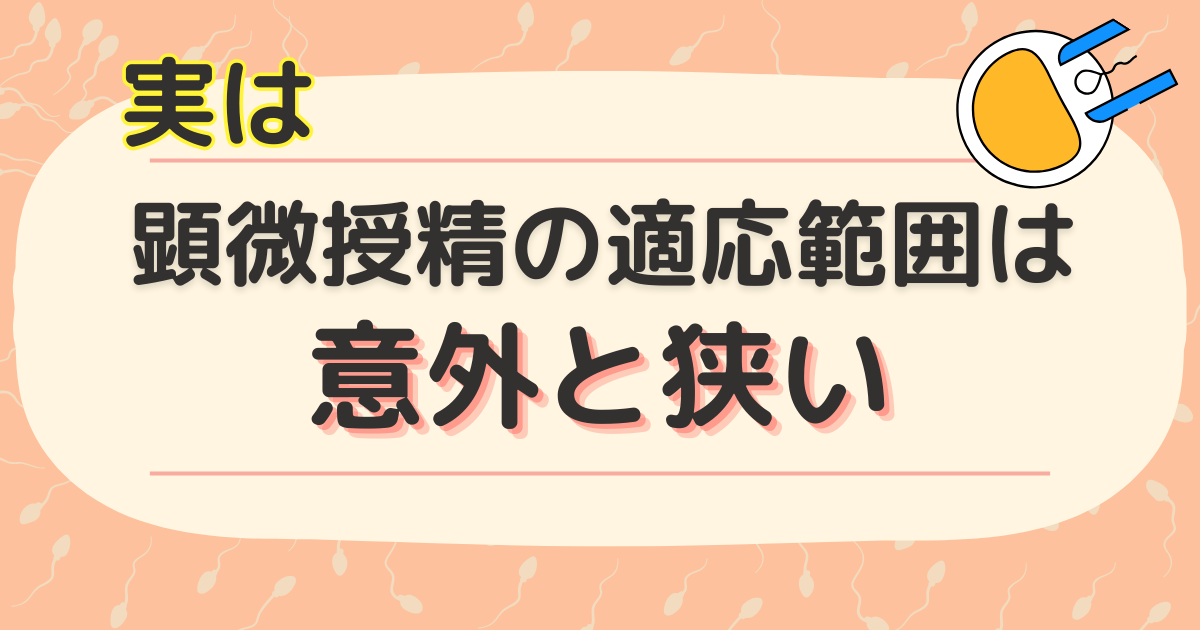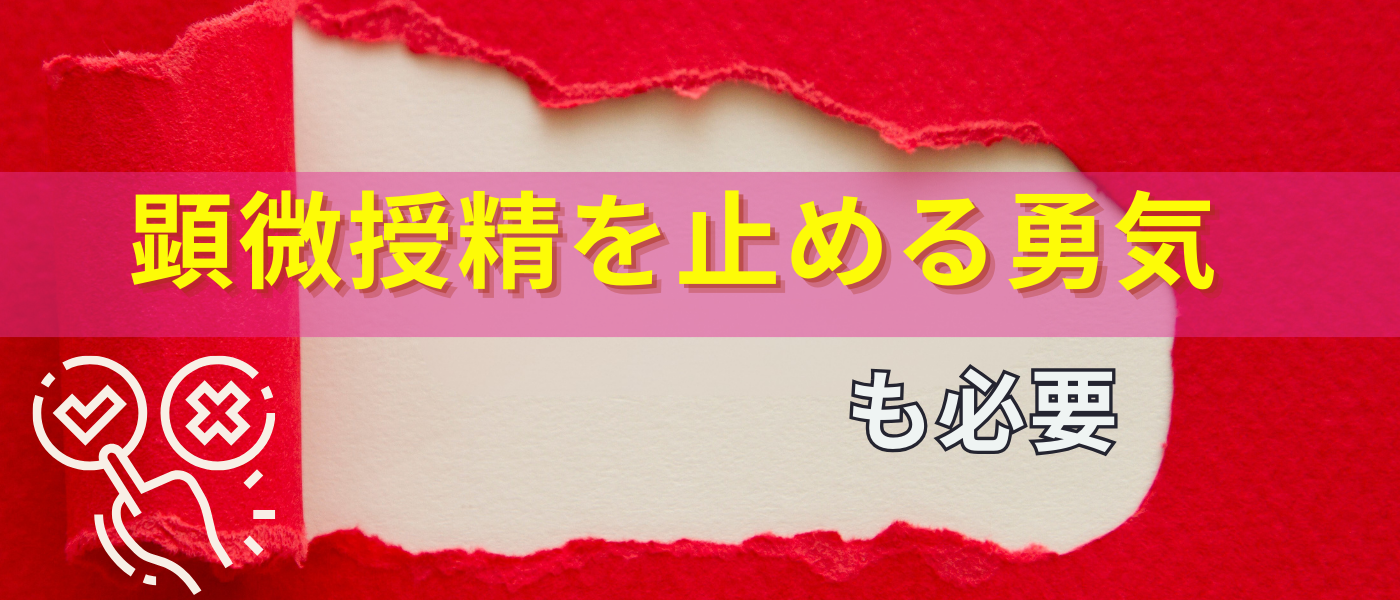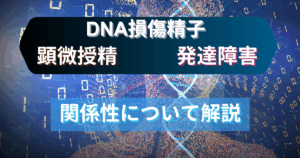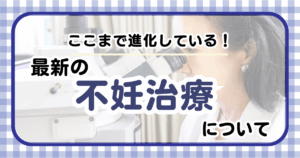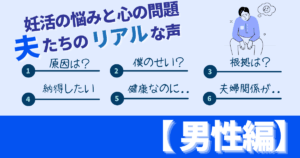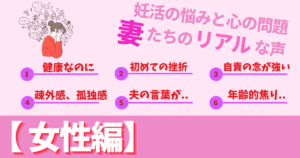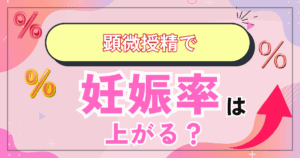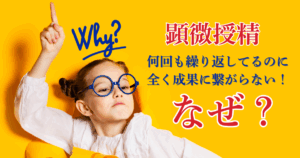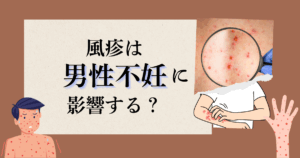顕微授精は人工的に授精を可能にする技術ですので、高い受精率を期待できます。また受精に必要な精子が たったの1匹でいいので、精子が極端に少ない男性にとっては、顕微授精が夢の治療法に思えることでしょう。その利便性から顕微授精の適応範囲が広がり、現在では精子の良い方から悪い方までフルレンジで実施され、生殖補助医療による受精法の約80%を占めるまでになりました。しかし、最新の不妊治療の項目で解説しましたように、精子選別・評価の技術精度の向上 および 人工卵管法の導入により、体外受精の適用範囲が広がり、顕微授精を回避できる症例も多い(結果として、顕微授精のリスクを回避できる)ことが明らかになりました。
見えないから気にならなかった!多様な精子機能異常を詳細に把握できるようになりますと、とてもじゃないけど怖くて刺せない!顕微授精を断念せざるを得ないケースが増え、その結果として顕微授精の適応範囲が狭くなることが予想されます。
目次
顕微授精は、精子の機能異常を補える訳ではない!
大半の精子の機能異常(精子の質の異常)は、生まれつきの遺伝子の問題(遺伝子異常)が原因で発症するケースです。一方で、顕微授精は、遺伝子の問題を克服できる技術ではありません。言い換えれば、精子の機能異常を補える技術ではありません。
この点をしっかりと認識していただき、健康な命の誕生に向けて、今後は顕微授精の治療限界、つまり「精子の質がどこまで悪くなったら治療を断念すべきなのか」について主治医と患者双方で論議する必要があります。
精子老化の原因とは?精子の妊孕性は予測可能なのか?
「顕微授精を止める勇気」も必要!
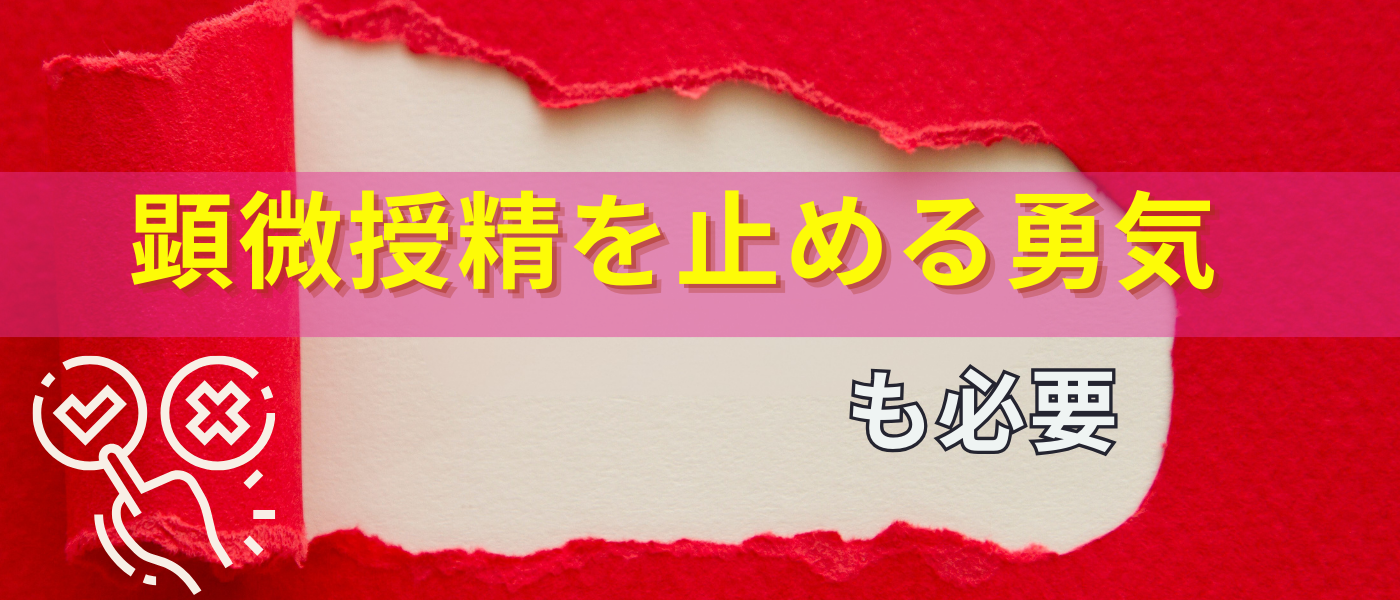
繰り返しになりますが、治療対象になる男性不妊の大半には、遺伝子異常(先天性)による多様な精子機能異常が認められます。精子異常を発症させる多様な遺伝子の異常に対する根本的な治療法は、おそらく登場しないでしょう。その点を踏まえますと『顕微授精を止める勇気』も必要な場合も出てきます。
今後は、安全な命の誕生に向けて、顕微授精の適応基準(適応範囲)を明確にする必要があります。実は、安全な顕微授精のストライクゾーンは狭い!ことを認識しましょう。
精子異常は治せるの?【専門医が解説】