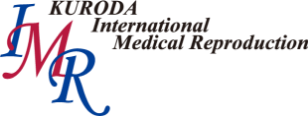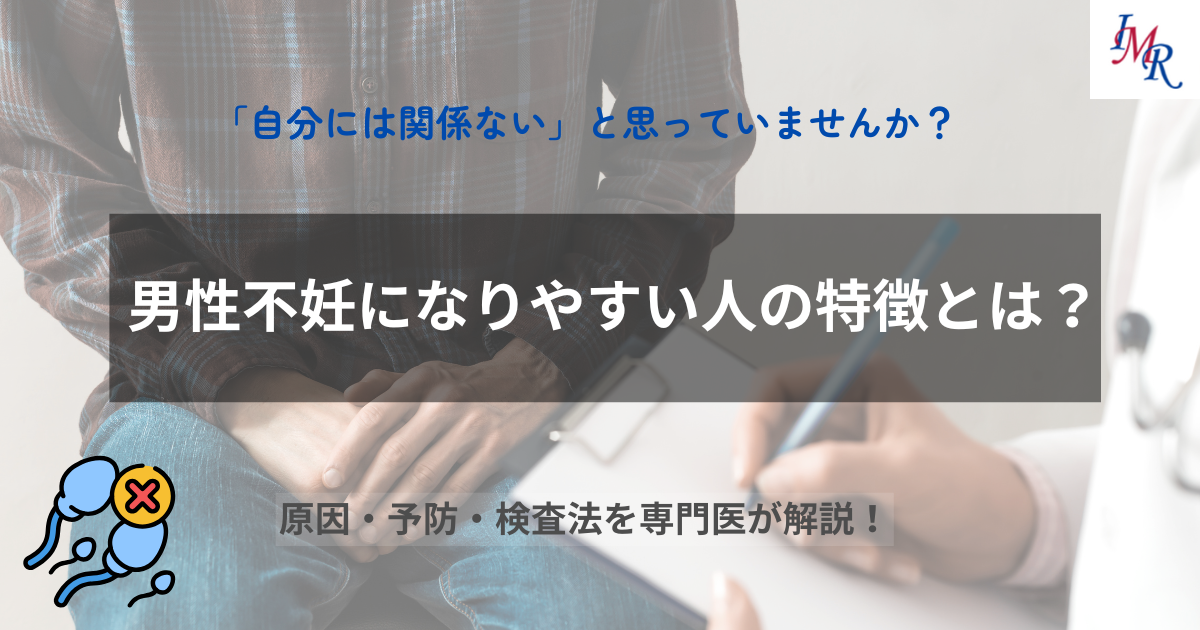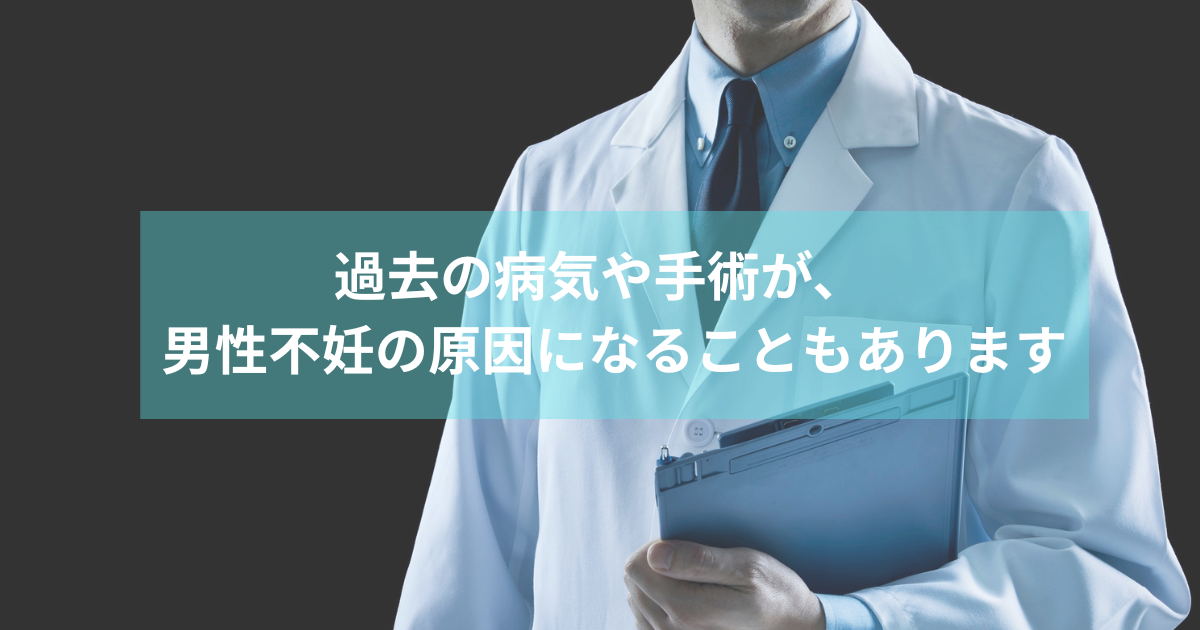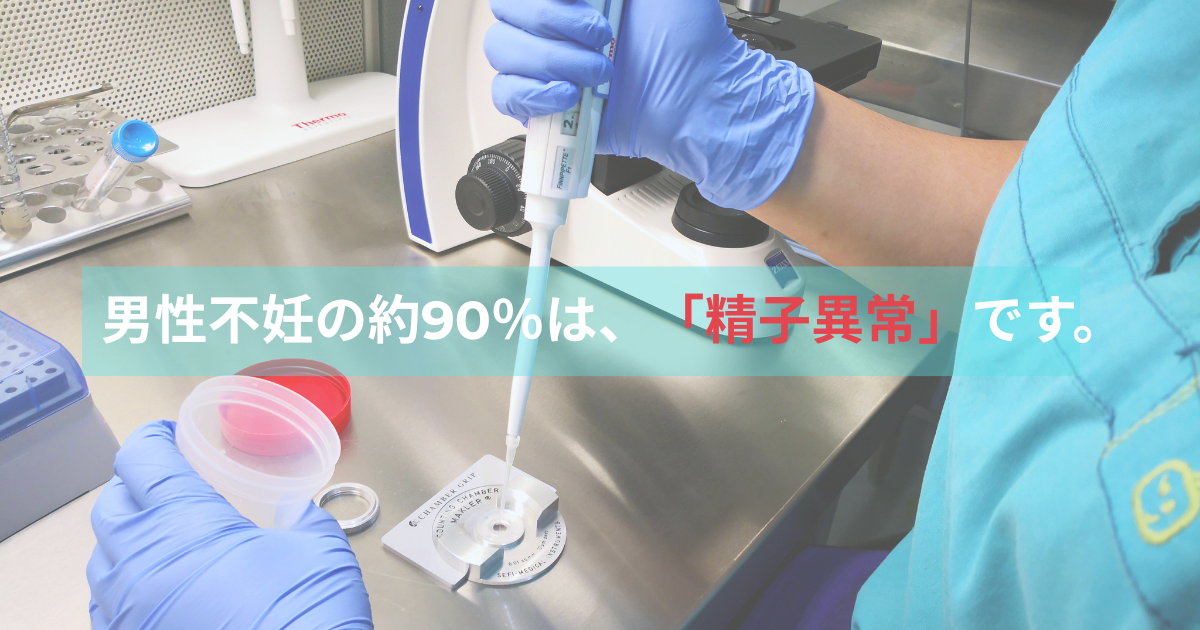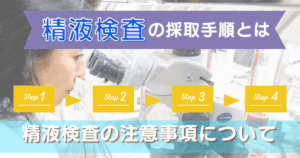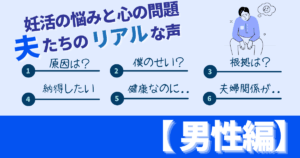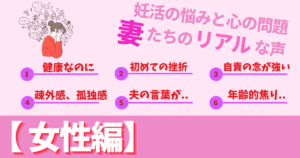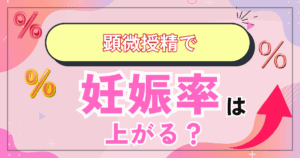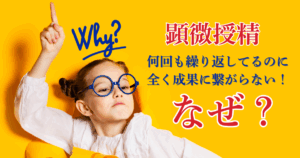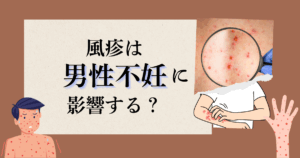不妊は一昔前まで「女性側の問題」というイメージが定着していましたが、現在では「不妊になる原因の約半数は男性側にあり、男性不妊が意外と多い」ということが広く知られるようになり、男性不妊に関する情報が世間に認知されつつあります。
この記事では、「男性不妊の原因と予防法」および「男性不妊か否かの検査法」について解説します。また「男性不妊になりやすい人の特徴」をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
不妊の約半数は男性側に原因がある「男性不妊」
世界保健機構WHOが2017年に実施した調査の報告によると、不妊の原因が女性のみに認められるケースは41%であるのに対し、男性のみに原因があるケースは24%、男女両方に原因があるケースは24%という結果でした。この数値を見ると、男性側に何かしらの原因があって妊娠できない「男性不妊」の割合は48%、すなわち全体の約半数を占めていることが分かります。つまり、不妊に悩むカップルのうち男性に原因があるケースは決して珍しいことではないのです。
参考:文部科学省 .「妊娠・出産に関して」
男性不妊になりやすい人の特徴
一言で男性不妊といっても その原因は様々ですが、男性不妊の約9割は、精子を上手く造ることができない「造精機能障害:ぞうせいきのうしょうがい」です。解りやすく言いますと、精子に何かしらの問題がある「精子異常」が、男性不妊の大半を占めるということです。精子異常の種類や程度も多様ですが、「男性不妊になりやすい人の特徴、傾向」には、以下のようなものが挙げられます。
生活習慣に問題があるケース

生活習慣に問題がある場合、健康被害が起こりやすくなるのは勿論ですが、精子にも悪影響を及ぼす可能性があります。生活習慣の問題によって精子異常が起きている場合、適度な運動やバランスのよい食生活、規則正しい生活を心がけることにより、精子の状態を改善できるケースもあります。
以下に詳しく解説しましたので、参考にしてください。
≈喫煙・カフェイン・アルコール≈
喫煙は活性酸素を増加させ、酸化ストレスを招きます。その結果、細胞のDNAや細胞膜、動脈の内膜等が傷付き、老化やがん、心臓の病気につながる可能性があります。体を構成する体細胞には、活性酸素で傷付いた細胞を修復したり、排除したりといった仕組みがありますが、長期間にわたって喫煙を習慣としている方の健康被害は避けられません。また喫煙者の精子異常率は高い傾向にあります。こういったいろいろな側面から考えると、喫煙はおすすめできません。
カフェインについても、長期的または過度に摂取すると、中枢神経系が過剰に刺激されます。これにより高血圧をはじめとするさまざまな健康被害を招く上、精子にも悪影響を及ぼします。健康を維持するためにも、精子のためにも、カフェインの摂取量は常識的な範囲に留めましょう。
アルコールに関しては、分解能の個人差が大きいため、どの程度精子に影響するのかは一概には言えません。とはいえ過度な飲酒や長期間にわたる飲酒は、肝硬変や痴呆、がん等との関連性が否定できませんので、カフェインと同じく常識的な量のアルコール摂取をおすすめします。
運動
日々の診療の中で、「過度な運動をすると活性酸素が増えて精子に悪い影響を及ぼすのでは?」という心配をされている方が多いような印象があります。
人の体は、過度な運動をすると活性酸素が増え過ぎた状態(酸化ストレス)になります。このとき、細胞のDNAや細胞膜、動脈の内膜等が傷付いてしまうことがあるため、結果として、老化やがん、心臓の病気につながる可能性が生じることは事実です。
しかし、私たちの体の細胞には、活性酸素で傷付いた細胞を修復したり、排除したりする仕組みがありますので、少しくらいの激しい運動で活性酸素が増えた状態(酸化ストレス)に神経質になる必要はありません。
むしろ、運動不足の場合は積極的に改善しましょう。体の健康を維持するにはある程度の新陳代謝を保つ必要がありますが、慢性的な運動不足に陥ってしまっている人は、その分 新陳代謝も低下します。新陳代謝は健康的な精子を造るためにも重要なため、運動不足の方は、自身の体力・ペースに合った運動習慣を身に付けることが大切です。
食生活
日々の診療の中では、「活性酸素を減らそう」と抗酸化物質を含むサプリメントを摂取している人が多いことにも気付かされます。しかし、サプリメントは全ての活性酸素に対応しているわけではありません。例えば、ビタミンC・ビタミンEはサプリメントで摂取するよりも、食事から摂取する方が効果的です。パプリカ、ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜や、お茶、大豆などを積極的に取り入れるようにして、バランスの良い食事を心がけてください。
【重要ポイント】抗酸化物質を摂取することは体にとって良いことですが、日常生活を送る中で発生するレベルの活性酸素や酸化ストレスは、通常であれば精子の異常に直結するような心配はないといえます。
サウナ・高温度の長風呂
精巣は体温より2~3度低い場所で正常に機能しますので、精巣が長い時間 熱に晒されると、精子の状態が悪くなる可能性があります。ですから、長時間のサウナや高温度の長風呂は避けた方が無難ですが、精巣で精子を造る機能(造精機能)が正常な人であれば精巣に十分な余力がありますので、一時的な温度上昇による精子への影響は極めて低いと考えてよいでしょう。
デスクワーク・長時間の運転
デスクワークや長時間の運転などで毎日長い時間同じ姿勢でいると、下半身の血行不良を招き、精子を造る精巣に悪影響を及ぼす可能性があります。
日々の診療の中では「ノートパソコンを膝に置いて作業することで、精巣の周囲に熱が溜まり、造精機能に障害を与えるのではないか?」という質問も多いです。
最近のノートパソコンは省電力であり、発熱は最小限に抑えられています。パソコンの熱による悪影響よりも、長時間同じ姿勢で作業を続けることによる、下半身の血行不良の方が心配です。もしかしたら、血行不良が精巣に悪影響を及ぼすことを懸念して、「ノートパソコンが良くない」といった噂が飛び交っているのかもしれません。同じ姿勢で長時間の作業をすることによる血行不良に注意してください。
ストレス
過度なストレスが健康被害を招くことは言うまでもありませんが、ストレスは精子にも悪影響を与えます。そのため不妊治療中は、上手にストレスを解消できるように過ごしましょう。
肥満
肥満は、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、心血管疾患などの生活習慣病のみならず、数多くの疾患を招いてしまいます。健康維持には、肥満の予防と対策が欠かせません。
また肥満によって これらの基礎疾患が発症すると、造精機能が障害されるケースもあります。適度な運動やバランスのよい食生活を心がけ、規則正しい生活を送り、肥満を予防しましょう。
コラム:男性の妊活でサプリは精子に有効? 生活習慣も含めて詳しく解説
病歴や過去に手術をされたケース
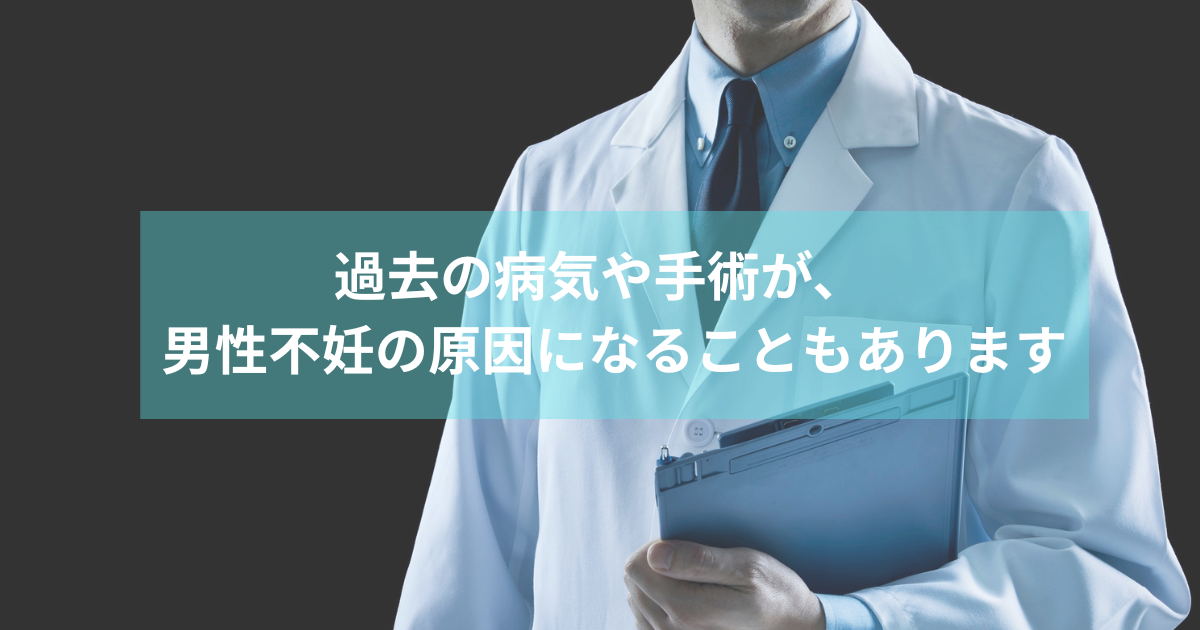
生活習慣に問題がなくとも、過去の病気や手術が原因で男性不妊となるケースもあります。主な疾患や手術をご紹介します。
精索静脈瘤
精索静脈瘤という血管異常がある場合、異常の程度によっては、造精ラインが障害されることがあります。外科的手術にて造精ラインの回復を期待できるケースもありますが、中には治療効果がみられないこともあります。
停留睾丸
停留睾丸とは、胎児のころ腹腔内にある精巣が生後数か月たっても陰嚢の中におりてこない病態をいいます。停留睾丸の数%は腫瘍化しますので、思春期までに精巣固定術による治療が考慮されますが、治療を行う場合は大半が造精機能障害を伴います。
精巣外傷後
事故などにより精巣に外傷を受けた場合、造精機能障害を伴うことも少なくありません。外傷の程度によっては造精ラインの一部が残ることもありますが、重度な精巣外傷の場合には造精機能障害を伴います。
おたふくかぜ(耳下腺炎)罹患後の耳下腺炎性精巣炎
おたふくかぜ(耳下腺炎)に罹患した後に高熱が続き、その影響で精巣に炎症が起きる場合があります。これを耳下腺炎性精巣炎といい、既往がある場合に造精機能が障害されます。
精巣上体炎後
精巣上体炎という、精巣上体という細い管に炎症が起こると、精子が通過するライン(精子輸送路)が閉塞されて無精子症になることがあります。治療法としては、顕微鏡下精巣上体精管吻合術が考慮されますが、精路再建が困難な場合もあります。
過去の抗がん剤治療や放射線治療などの実施
抗がん剤や放射線等を使う治療の目的は癌細胞を殺すことですが、同時に造精機能を強く傷害する可能性があります。
鼠径ヘルニア手術後・精管切断術後
鼠径ヘルニア手術後や避妊手術としての精管切断手術後等の精管閉塞により、閉塞性無精子症になる場合があります。治療法としては顕微鏡下精管精管吻合術が考慮されますが、精路再建が困難な場合もあります。
男性不妊の可能性が高い人の特徴
前述の通り、生活習慣に大きな問題があると思われるケースや、これまでに罹患した病気や過去に手術をした病歴があるケースでは、男性不妊の可能性が高くなります。ここでは、とくに男性不妊を疑うべき体の変化を2つご紹介します。
陰嚢の状態が過去と比べて変化したケース:陰嚢で分かること
睾丸(正式には精巣と言う)を包む袋のことを陰嚢と言いますが、思春期と比べて睾丸が「小さくなった」「大きさに左右差が出てきた」「柔らかく張りがなくなった」「位置が陰嚢内の上方や鼠径部にある感じがする」といった変化や、「陰嚢を触ると形状のものに触れたりする」など、これまでの状態と異なる点が認められた場合には、泌尿器科を受診してみることが大切です。精巣のトラブルが造精機能の低下につながるケースも少なくありません。
精液の状態が過去と比べて変化したケース:精液で分かること
射精した時の感覚として、過去に比べて精液の量や色に変化があるように感じることがあるかと思います。例えば、精液量が「極めて少ない」もしくは「物凄く多くなった」、乳白色だった精液が「無色透明になった」などの変化です。
「何か異常が起きたのでは?」と不安になる方も多いかと思いますが、ご安心ください。前立腺と精嚢腺の分泌液の量は、射精がうまくできたか否かにより大きく変動しますので、精液量は多くなったり少なくなったりして当然です。射精時の分泌液量が多ければ精子濃度は低くなり、分泌液量が少なければ精子濃度は高くなります。その結果として、精液の色も濃く見えたり薄く見えたりするのです。
しかし一方で、造精機能障害や逆行性射精が精液量や色に変化をもたらすケースもありますので、これまでの状態と異なる点が認められた場合には、泌尿器科を受診してみることも大切です。中でも精液の色が「血が混ざっているような薄い赤色になった」場合は、射精経路にトラブルが起きている可能性がありますので早めに受診してください。
男性不妊の原因
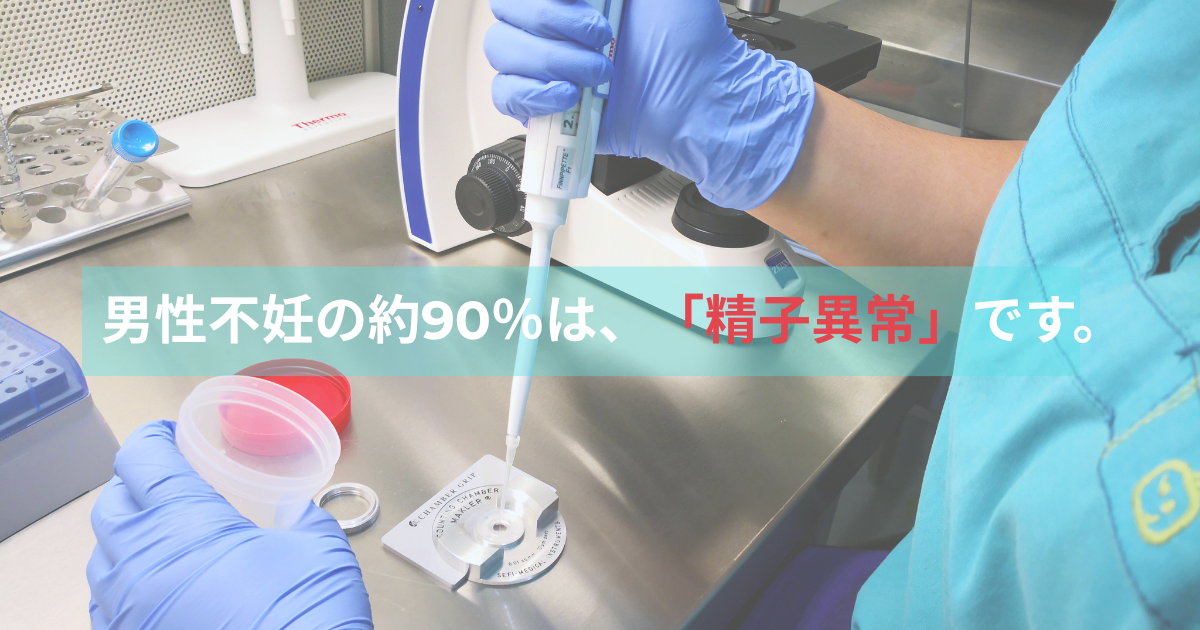
冒頭でも申し上げましたが、不妊の原因の約半分は男性側に原因がある「男性不妊」です。男性不妊の原因は大きく、① 造精機能障害、② 精路通過障害、③ 性機能障害の3つに分けられますが、男性不妊の約90%は、精子が造られる過程に何かしらの異常が生じて精子を上手く造ることができなくなる「造精機能障害」すなわち「精子異常」のケースです。
本項では、男性不妊の大半を占める造精機能障害(精子異常)と、その他の男性不妊の原因を正しく理解していただくために、具体的な症状を挙げて分かりやすく解説します。
造精機能障害1:隠れ精子異常による造精機能障害
造精機能障害には、生まれながらにして精子形成過程に異常が生じて精子を上手く造れない場合(先天性)と、生まれた後に特定の原因によって問題が発症する場合(後天性)があります。
原因を特定できる後天性のケースより、原因を特定できない先天性の造精機能障害の方が多いため、不妊治療において精子の問題は深刻です。
一般的には造精機能障害、精子異常と診断される際には、「精子産生量の低下:精子数の減少」「運動能の低下:運動率の低下」「形態異常率の増加:奇形率の増加」という、普通の顕微鏡(位相差顕微鏡)で見てすぐに判る異常が指摘されます。しかし、生殖補助医療の治療対象となる精子異常の大半は、位相差顕微鏡で検知することができない、精子の中に隠れ潜んだ異常として発現してきますので厄介です。これを『隠れ精子異常』と言っています。実は、位相差顕微鏡で観察して精子数も多く、運動率も高く、WHOの基準を満たして、健康な精子に見えた運動精子の中に、隠れ精子異常が沢山含まれています。
【重要ポイント】隠れ精子異常は、どういった異常なのでしょうか?リスクは?
解りやすく説明しますと、精子DNA(遺伝情報)が傷ついていたり、精子を包んでいる膜(細胞膜)が損傷していたり、受精するところ(先体)に問題が認められたり、多様な精子機能の異常を言います。隠れ精子異常の種類と程度には個人差がありますが、複雑にクロストークしているケースが多くみられます。
最も重要な点は、隠れ精子異常の背景には『新生突然変異という遺伝子異常=先天異常』が関与していますので、根本的な治療法がなく、治療が難航する傾向にある点です。さらに最も怖い点は、隠れ異常精子が人工的に受精させられて妊娠・出産に至った場合に、生まれてくる子供に何かしらの影響を与えるリスクがある(詳細は後述)という点です。
隠れ精子異常の存在は、分子生物学的な手法による高精度な精子検査(詳細は後述)をしなければ明らかになりません。繰り返しになりますが、一般精液検査で用いる位相差顕微鏡では隠れ異常を検出することができませんので、隠れ異常が見逃されたまま間違った治療を薦められてしまうケースも少なくありません。ご注意ください。
造精機能障害2:無精子症
無精子症とは、精液中に精子が全く見られない状態をいいます。閉塞性と非閉塞性による無精子症に分けられますが、造精機能障害の中では最も重症になり
閉塞性無精子症は、精巣で造られた精子が通過するライン(精子輸送路)が閉塞されていることが原因で無精子症になっているケースです。代表的なものとして、精巣上体炎罹患後、鼠径ヘルニア手術後、避妊手術(精管切断)後の閉塞性無精子症があります。
このケースでは、精巣内に少しでも精子を造るラインが残っている限り、精巣内から精子を採取して顕微授精に展開する治療法(TESE:Testicular Sperm Extraction)が適応されます。
【重要ポイント】ただし、精巣から採取した精子は未成熟な状態にあり、一見元気に泳いでいる精子(運動精子)でも、隠れ異常精子である可能性があります。その隠れ異常精子を用いたTESEにより生まれた子供に何かしらの異常が発症する可能性・リスクを否定できません。ここに命を誕生させる不妊治療における最も怖い点があります。
一方で、非閉塞性無精子症は、生まれつき精子の設計を支配する遺伝子に異常(先天的な原因)があり、その結果 無精子症となっている場合です。このケースは、自身の精子による治療は困難となります。
造精機能障害3:精子無力症
WHOの基準では、精液中における健康な精子の総運動率は42%以上と定められており、運動率が42%以下になると精子無力症と診断されます。
精子の中片部(頭部と尾部をつなぐ部分)にはエネルギーを産出するミトコンドリアという小器官が存在しており、このミトコンドリアにおけるエネルギー調節機構に問題があると運動能(運動率)が低下する可能性が指摘されています。一方で、ミトコンドリア機能が正常でも泳ぐために必要な尾部の細胞膜が脆弱な精子の運動能は低くなります。ですから、精子無力症の原因が「中片部ミトコンアドリアの問題なのか?」「尾部細胞膜の問題なのか?」を見極めることが重要です。
しかしながら、精子無力症の背景には遺伝子の問題(先天的な原因)が関与しているケースも多く、この場合は改善を期待することは困難です。一方で、後天的な原因としては精索静脈瘤などがあり、中には手術により改善が期待できるケースもあります。しかし残念ながら、精子無力症と診断された場合の多くは、生殖補助医療の適応になります。
造精機能障害4:乏精子症
WHOの基準では、精液中の精子数が 1ml中 1,600万未満の場合に乏精子症と診断されます。乏精子症に対する治療法として、ホルモン療法や漢方、サプリメントなどいろいろと言われていますが、正直なところ効果が認められない場合が多いのも事実です。とくに生殖補助医療の治療対象になる乏精子症の多くは、精子無力症と同様に遺伝子の問題(先天的な原因)が関与していますので根本的な治療法はありません。一方で、精索静脈瘤など後天的な原因によるケースの中には手術により改善が期待できる場合もありますが、精子無力症と併せて発症することも多く、生殖補助医療の適応になることが殆どです。
精路通過障害
精路通過障害は、造精機能には問題がありませんので、うまく精子を造ることができます。しかし、精子輸送路に問題があり、造られた精子が通過することができません。
精巣上体炎後・鼠径ヘルニア手術後・精管切断手術後
精巣上体という細い管に炎症が波及して精子が通過するライン(精子輸送路)が閉塞され、無精子症になることがあります。この病態を精巣上体炎といい、顕微鏡下精巣上体精管吻合術による精路再建が考慮されますが、改善が困難な場合もあります。
その他、鼠径ヘルニア手術後や避妊手術としての精管切断術後の精管閉塞により、閉塞性無精子症になる場合もあります。顕微鏡下精管精管吻合術による精路再建が考慮されますが、改善は困難な場合もあります。
性機能障害
性機能障害は、精路通過障害と同様、精巣で精子を造るラインには問題がなく、正常な造精機能を備えていますので問題なく精子を造ることができます。また精子輸送路にも問題がありませんので、造られた精子が通過することも難なくできます。しかし勃起や射精といった性機能に問題があり、性行為を完了することができません。
糖尿病・手術による神経損傷
糖尿病や手術による神経損傷等の影響で、内尿道口の閉鎖が不完全になり、射精時に精液が射出されずに膀胱内に排出されてしまうことがあります。この状態を逆行性射精といい、治療法としては、内尿道口の閉鎖不全を改善させる目的で交感神経α刺激薬(塩酸イミプラミン、アモキサピン)を使用します。この治療は効果が得られない場合も往々にしてあるため、最終的には射精後に排尿し、可及的速やかに高度な精子分離技術を用いて精子の回収に努めることになります。
脊髄損傷後・リンパ節郭清を伴う手術後
脊髄損傷後やリンパ節郭清を伴う手術の影響により、射精に関わる神経機能が損傷され、無射精になる場合があります。治療法としては、バイブレーターによる振動刺激、電気射精法(経直腸的に精嚢、前立腺を電気刺激して射精を誘発する方法)がありますが、なかなか効果が得難い傾向にあります。
その他
ストレスや糖尿病、多発性硬化症、薬剤(α1ブロッカー)等の影響で、勃起障害ED(有効な勃起が起きない状態)になり、性行為がうまくいかない場合があります。また性行為まではできるものの、射精障害(腟内で射精することが困難)になる場合もあります。
また不妊治療においては、「タイミング指導」という、予測した排卵日に性行為をとるように指示をする場合もあります。タイミングに固執してしまうと性行為そのものの障害を来たしたりすることがあります。
男性不妊になりやすい人・可能性がある人は、高精度な精子検査を受けてください
現状の男性不妊の診断は、WHO基準値による精液検査の結果に基づいていますが、診断精度は決して高くありません。その診断基準は、通常の位相差顕微鏡で精液を観察し、見た目だけで「精子形態」「精子数」「運動率」等を算出するというものです。具体的にいえば、「精子の形が悪い=奇形精子症」「精子が確認できない=無精子症」「精子数が少ない=乏精子症」「運動率が低い=精子無力症」など、一つでも基準値を満たしていなければ「男性不妊=造精機能障害=精子異常」と診断されます。
その診断基準による男性不妊の怖い点は、「精子の形や動きが悪い」とか「精子が少ない」という見た目だけで「精子に異常がある」と判定することができない、見た目ではわからない隠れ精子異常の存在が見逃されている点です。つまり、WHO基準診断では異常なしと判定されてしまうような見た目が正常な運動良好な精子の中にも、隠れた多様な異常(精子内部の構造や機能の異常)を持った精子が多いという点です。とくに生殖補助医療の治療対象になる不妊男性の精子には、その傾向が強く見られます。
前述の通り、隠れ精子異常は分子生物学的な手法で特別な顕微鏡を用いて観察することにより初めて明らかになる異常ですので、通常の位相差顕微鏡では検知できません。そのため、一般精液検査では隠れ精子異常が見逃されてしまい、その結果間違った治療を薦められる危険性があります。
また大半の隠れ精子異常の背景には、新生突然変異という遺伝子異常が関与しています。言い換えれば、先天的に精子形成に関わる遺伝子に異常があることが原因で隠れ精子異常が起きる場合があるということです。遺伝子異常を克服できる技術、治療法はありませんので、治療も難航します。ここに男性不妊治療の難しさがあります。
【重要ポイント】妊活を開始するにあたり最も重要な点は、なるべく早い時点で(できれば治療を開始する前に)、隠れ精子異常の有無を正確に見極めることができる精子精密検査を受けておくことです。その結果から、適正な男性不妊治療の方向性が見えてきますので最も効率的です。
さらには精密検査の結果、「隠れ精子異常がある」ことが明らかになった際には、「なぜ?」という辛い思いになりますが、その気持ちを乗り越えて「自身の精子のタイプに最適な治療法は何だろう?」と前向きに捉えていただきたいです。
まとめ
男性不妊は決して珍しくはありません。しかし過去には不妊は女性の問題と考えられていたため、ショックを受ける男性も少なくないと思います。
黒田インターナショナルメディカルリプロダクション(黒田IMR)は、完全予約制・完全個室制・院長による完全個別指導制の男性不妊専門クリニックです。患者さま一人ひとりに必要な検査を行った上で適切な治療プランを立てていきます。不妊症は一括りにできないという考えのもと、オーダーメイド制の医療を行っています。
完全個室制ですので安心してデリケートな質問や相談ができます。「男性不妊かも」と不安になっている方は、ぜひ相談先として考えてみてください。